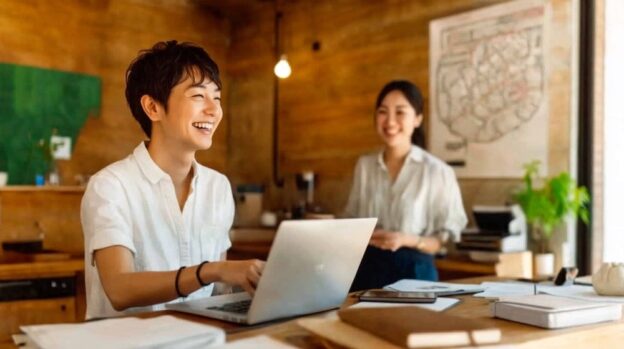「え、マジで月5万円で新潟に住めるの?」
このフレーズ、最近よく聞かれるんです。
名古屋から新潟に移住して早3年目の私が、ついに重い腰を上げて”リアル”をお伝えします!
都会の喧騒から抜け出して、雪国で始める新生活。
想像するだけでワクワクしませんか?
でも現実はどうなの?って思いますよね。
私も最初は「田舎で仕事なんてあるの?」「冬の雪大丈夫?」と不安だらけでした。
でも実際に飛び込んでみたら、想像以上に暮らしやすくて、リモートワークとの相性も抜群だったんです!
今回は私の実体験をもとに、月5万円生活の具体的な内訳から、リモートワークの環境構築、地域コミュニティとの関わり方まで、包み隠さずお伝えします。
「もしかして私も新潟移住、アリかも?」と思えるヒントが見つかるはず!
この記事を読めば、家賃や食費などの具体的な出費の目安、仕事の見つけ方、地元の人との関わり方まで、新潟移住のリアルな姿が丸わかりです。
さぁ、新潟×リモートワークの可能性を一緒に探っていきましょう!
新潟×リモートワークのポテンシャル
新潟県は実は「隠れたリモートワーク適地」として、密かに注目を集めています。
データで見ると、2020年以降の移住者数は前年比30%増と、コロナ禍での地方移住ブームの恩恵を確実に受けています。
特に長岡市や上越市など、新幹線のアクセスが良い地域は、東京や大阪の企業に所属したままでも「週1出社」が可能なエリアとして人気上昇中です。
移住者のうち約40%がIT関連職という調査結果もあり、リモートワーカーの受け入れ体制が整いつつあると言えるでしょう。
1. リモートワークが根づく背景
コロナ禍は私たちの働き方を根本から変えました。
あれから数年経った今でも、多くの企業がリモートワーク体制を維持しています。
特にIT企業の多くは「フルリモート可能」「週1出社」といった柔軟な勤務形態を導入し、地方移住と両立する働き方が現実的になりました。
新潟県も2021年から「リモートワーク移住支援金」制度を開始し、最大100万円の補助が受けられるケースもあります。
私が以前働いていたスタートアップでも、社員の30%以上が地方在住というデータがありました。
オンラインでのコミュニケーションツールの進化や、クラウドサービスの普及によって、物理的な距離の制約はどんどん小さくなっています。
さらに、新潟県内の光回線カバー率は都市部とほぼ変わらず、Wi-Fi環境も整備されているため、テレビ会議やデータのやり取りもストレスフリー。
リモートワークに必要なインフラは十分に整っていると言えるでしょう。
2. 新潟ならではの”プチ贅沢”生活
新潟での生活コストは都会と比べると驚くほど低いんです!
例えば、私が住む長岡市の家賃相場は東京23区の約3分の1。
1LDKでも4万円台から見つかります。
これだけでも生活の余裕が全然違ってきますよね。
食費も地元産の野菜や米を直接農家から購入できるため、高品質なものをリーズナブルに手に入れられます。
私のお気に入りは、地元の農家さんが開く朝市で、新鮮な野菜を詰め放題500円で購入できること!
東京では考えられない「食の贅沢」が日常的に楽しめるんです。
もち米や日本酒も有名ですが、実は魚介類も豊富で、日本海の幸を都会の半額以下で味わえるのは大きな魅力です。
エンタメ費も都会より抑えられるため、その分を趣味や自己投資に回せるのもポイント高いです。
3. コミュニティ&SNSを活用した仕事探し
「新潟でどうやって仕事を見つけるの?」
これは多くの方が抱える疑問だと思います。
地方ベンチャーの求人は確かに都会ほど多くありませんが、逆に言えば競争率も低く、チャンスが見つけやすいのも事実。
私の場合は、移住前からTwitterで「#新潟移住」「#新潟ベンチャー」などのハッシュタグを検索して情報収集し、気になる企業の方とDMで直接やり取りしました。
この方法で現在の会社とつながることができたんです!
また、新潟には「ながおかコワーキングスペースChikyuBa(ちきゅうば)」のような施設もあり、ここで定期的に開催される交流会やイベントは仕事獲得の大きなチャンスとなっています。
リモートワーカー向けのSlackコミュニティも充実しており、「新潟リモートワーカーズ」には約300人が参加し、案件の紹介やスキルシェアが行われています。
移住前に参加しておくと、現地の情報収集や人脈作りがスムーズにできるのでおすすめです!
月5万円生活の内訳とリアル
実際に私が実践している「月5万円ベース生活」の内訳を大公開します!
もちろん、これはあくまで基本的な生活費であり、趣味や自己投資、貯金は別枠で考えています。
でも、この5万円をベースに考えれば、都会の半分以下のコストで快適に暮らせるのは事実です。
「え、マジで?」と思われるかもしれませんが、筆者の実体験に基づいた数字なので参考にしてみてください!
1. 生活コストのリアル
まず、私の実際の家計簿をベースに月の基本生活費を公開します!
1. 住居費:3万円
- 賃貸アパート(1K、築10年):家賃28,000円
- 水道光熱費:平均10,000円(冬は暖房費で+5,000円ほど増加)
- インターネット:光回線4,000円(キャンペーン適用後)
2. 食費:1万5,000円
- 自炊中心:約10,000円(地元産の野菜・米を活用)
- 外食:月4〜5回で5,000円(ランチは800円前後が多い)
3. 交通費:5,000円
- ガソリン代:5,000円(月によって変動あり)
- 公共交通機関:ほぼ使用せず
私の場合、家賃を抑えるために駅から少し離れた物件を選びました。
徒歩10分圏内にスーパーやドラッグストアがあるエリアを選んだので、日常生活には不便しません。
食費が安く抑えられるのは新潟の最大の魅力!
米どころなので、10kgのお米が2,500円程度で購入できますし、道の駅や農家の直売所では都会の半額以下で新鮮な野菜が手に入ります。
交通費については、車は必須と考えた方が良いでしょう。
私は中古車を60万円で購入し、ガソリン代と保険代を月々の出費として計算しています。
食費節約のコツ
新潟での食費節約には、地域ならではのテクニックがあります。
例えば、「おすそ分け文化」を活用するのが大事。
近所の方から野菜をいただくことも多く、お返しに得意な料理を作って持っていくなど、コミュニティの中で食材が循環しています。
また、雪国ならではの保存食文化も活用できます。
大量に手に入った野菜は漬物にしたり、乾燥させたりすることで長期保存が可能です。
2. リモートワークに必要な環境投資
リモートワークを快適に行うためには、初期投資も必要です。
私の場合は以下のような環境を整えました。
1. 通信環境
- 光回線の新規契約:初期工事費実質無料(2年契約条件)
- モバイルWi-Fi(バックアップ用):月額3,000円
2. 作業環境
- デスク・チェア:中古で15,000円
- ディスプレイ:新品で20,000円
- Webカメラ・マイク:10,000円
- 照明:5,000円
3. ソフトウェア関連
- クラウドストレージ:月額1,000円
- 動画編集ソフト:年間サブスク15,000円
リモートワークの環境整備には、一時的に約5〜10万円の投資が必要でした。
ただし、これらは一度購入すれば長く使えるものなので、長期的に見ればコスパは良いと考えています。
特に重要なのは、安定したインターネット環境です。
光回線が引ける物件を選ぶか、事前に電波状況を確認しておくことをおすすめします。
Zoom会議が頻繁にある場合は、マイクとカメラの質にこだわると印象が全然違います!
3. 新潟移住者としての筆者体験談
実際の私の1日のスケジュールをご紹介します。
平日の過ごし方(夏)
- 6:00 起床、近所の公園で軽いジョギング
- 7:00 朝食・シャワー
- 8:00 リモートワーク開始(自宅作業)
- 12:00 ランチ休憩(自炊や近所のカフェ)
- 13:00 午後の仕事(週2回はコワーキングスペースで作業)
- 17:00 リモートワーク終了
- 18:00 趣味の時間(動画編集や地域活動)
- 20:00 夕食・自由時間
- 23:00 就寝
一番の変化は「通勤時間がなくなった分、趣味や自己投資の時間が増えた」こと。
私は空いた時間で動画編集のスキルを磨き、副業として月3〜5万円の収入を得られるようになりました。
また、週末には新潟の様々な場所を訪れて動画撮影し、SNSでの発信も積極的に行っています。
これが「新潟の魅力発信」につながり、さらに仕事の依頼に発展することも多いんです。
地元の季節イベントへの参加も楽しみの一つで、お祭りや収穫祭などを通じて地域の方々とのつながりも深まっています。
移住後に直面するギャップと対処法
さて、ここからは移住後に実際に直面した「あるある」や「想定外」の出来事とその対処法をお伝えします。
事前に知っておくことで、心の準備ができますよ!
1. 冬の雪対策と季節行事
まず、新潟の冬は想像以上に雪が多いです。
私が住む長岡市では、例年1〜2mの積雪があります。
対策としては以下の準備が必須です:
1. 住居の雪対策
- 雪下ろし道具の準備(スコップ、スノーダンプ)
- 屋根の雪止め確認(アパート選びの際にチェック)
- 窓の断熱対策(断熱カーテン、窓用シート)
2. 防寒対策
- 本格的な防寒着への投資(一見高額でも長く使えるものを)
- 滑りにくい靴(雪道用のブーツは必須)
- 車の冬タイヤ(11月中旬までに準備)
3. 光熱費の上昇対策
- 暖房費は冬場、夏より月5,000円ほど上昇
- 部屋を区切って暖める工夫
- こたつやホットカーペットの活用(電気代の節約に)
でも冬の新潟は大変なことばかりではありません!
「長岡まつり大花火大会」や「十日町雪まつり」など、雪国ならではの季節行事が豊富です。
むしろ雪を楽しむ文化が根付いているので、地元の人たちは冬を楽しみにしているんですよ。
私も最初は雪かきに苦労しましたが、今では近所の方と一緒に作業する時間が交流の場になっています。
2. クルマ社会への適応
新潟は完全なクルマ社会です。
公共交通機関は都会と比べるとかなり限られており、バスも本数が少ないエリアが多いです。
私も移住当初は車なしで生活していましたが、3ヶ月で限界を感じて中古車を購入しました。
1. 車の必要性
- 買い物、通院、レジャーなど、ほぼすべての活動に必要
- 雪道運転のスキルも必要(初めての冬は要注意)
- 年間維持費:約15〜20万円(税金、保険、車検、ガソリン)
2. 公共交通機関の活用法
- 主要駅周辺に住むことで利便性アップ
- 地域のコミュニティバス情報を事前に調査
- カーシェアサービスの活用(新潟市内ではカーシェアも増加中)
地方ならではのクルマ文化の面白さもあります。
例えば「車中泄」という地元の言葉があり、車の中で休憩したりおしゃべりしたりする文化があるんです。
ドライブスルーのお店も多く、車を中心とした生活様式が確立されています。
車の維持費は負担に感じるかもしれませんが、移動の自由度が格段に上がるため、生活の質は確実に向上します。
3. 地域コミュニティに馴染むコツ
移住当初、一番の不安は「地域に馴染めるか」ということでした。
実際、新潟の方言や慣習、地域特有のコミュニケーションスタイルに戸惑うこともあります。
しかし、いくつかのポイントを押さえれば、スムーズに地域に溶け込めるはずです。
1. 積極的な参加が鍵
- 町内会や自治会の行事には極力参加する
- 地域のゴミ拾いや草刈りなどの共同作業に顔を出す
- 挨拶は必ず行う(地方では挨拶の価値が高い)
2. SNSの活用
- Facebookの地域グループに参加
- 「新潟移住者コミュニティ」などのオンラインコミュニティを活用
- 地元イベント情報を定期チェック
3. 移住者同士のネットワーク
- 移住者向けの交流会に参加
- コワーキングスペースでの人脈づくり
- 趣味を通じたコミュニティ探し
私の場合、最初の一歩として「新潟移住女子会」というオンラインコミュニティに参加しました。
そこで知り合った先輩移住者から地域の情報や暗黙のルールを教えてもらえたのが大きかったです。
また、自分のSNSで「新潟での生活」を発信することで、同じ趣味を持つ地元の方から声をかけてもらえることも増えました。
無理に地元に溶け込もうとするより、まずは同じ境遇の移住者と繋がり、少しずつ輪を広げていくアプローチが効果的です。
まとめ
新潟での月5万円生活とリモートワークの組み合わせは、想像以上に実現可能で充実したものだと実感しています。
都会の喧騒から離れ、豊かな自然と美味しい食に囲まれながら、自分のペースで仕事ができる生活は、まさに「新しい働き方・暮らし方」のロールモデルと言えるでしょう。
今回お伝えした内容をまとめると:
- 基本生活費は月5万円から可能(家賃3万円、食費1.5万円、交通費0.5万円)
- リモートワーク環境の初期投資は約5〜10万円
- 雪対策や車社会への適応が必要だが、地域ならではの楽しみも多い
- コミュニティ形成はSNSや移住者ネットワークを活用すると効果的
もちろん、すべてがバラ色というわけではありません。
冬の厳しさやインフラの制約、仕事の選択肢の少なさなど、都会と比べると不便に感じる部分もあります。
しかし、それを補って余りある「生活の質」の向上があると私は感じています。
時間的・経済的な余裕が生まれることで、本当にやりたいことに集中できる環境が手に入るのです。
私自身、移住してから「地元の魅力発信」という新しい仕事にチャレンジし、充実した日々を送れているのはその証拠かもしれません。
「地方こそチャンスがある!」
これは私の実体験から生まれた確信です。
新潟への移住を検討している方、リモートワークでの地方生活に興味がある方の背中を少しでも押せたなら嬉しいです。
最後に一言、「百聞は一見にしかず」。
ぜひ一度、新潟に足を運んでみてください。
きっと想像以上の魅力が待っていますよ!
移住のリアルについて、さらに詳しく知りたい方はTwitter(@kana_niigata)でDMをお待ちしています。
一緒に新潟の可能性を広げていきましょう!