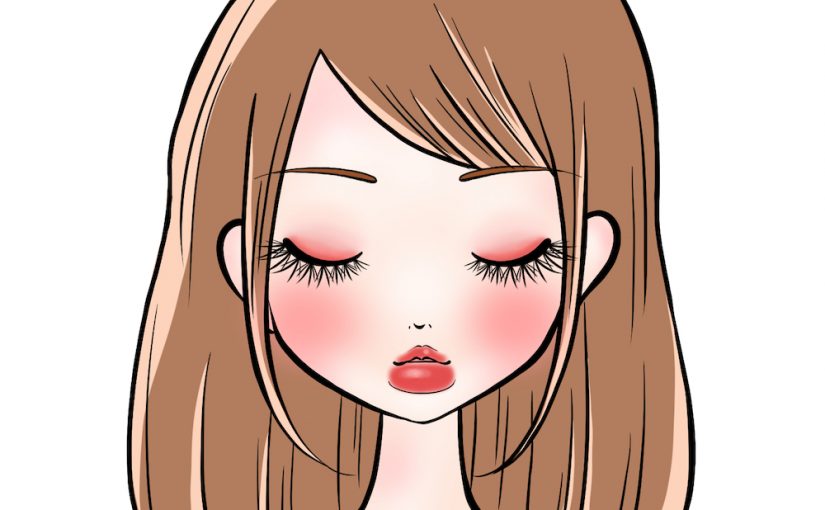「畑恵さんのような政治家に期待したい」
「日本の政治の歴史を学びたい」
「女性政治家の活躍と歴史を知りたい」
日本は先進諸国と比べると、政治面では非常に保守的な国だといわれています。
とくにアメリカ合衆国に対しては、非常に低い姿勢となっており、常にアメリカに対する行動はイエスマンであると現地の新聞社やジャーナルでは評価をされています。
中国や韓国に対しても領海の進入があった際でも、「遺憾の意」としか発言をしないのが日本のやりかたといえるでしょう。
平和主義であると言えば聞こえが良いのですが、もしも有事が発生した際でも言葉のみで意見と意志を表現するだけでは、本土や国民を守ることはできません。
もっと積極的で力強い指導者が国を治めるべきだといえるでしょう。
いまでは男女平等というのが国際的な見解であり、19世紀や20世紀初頭のような男性のみが指導者になっているという国は数少なくなりました。
2021年現在では世界各国で女性首相が数多く存在をしており、ノルウェーやスイス・ドイツなどの欧州の大都市でも女性が指揮を執っている国があるほどです。
そこでここでは、畑恵氏など日本における女性政治家の活躍と歴史を詳しく見ていくことにしましょう。
あわせて読みたい
【宇田先生に聞く】個人投資家になる人が増えている理由
女性政治家がはじめて国内で誕生したのは大正時代の中期
まず国内では現在、与党は計2つ・野党は計5つという勢力図とあっています。
このうち、2つの野党で女性が党首を務めたことがあり、現在でも政調会長や副代表というポジションで活躍をなされているわけです。
まず女性政治家がはじめて国内で誕生したのは、大正時代の中期です。
大正デモクラシーという運動は、どなたでも教科書で目にしたことがあるでしょう。
それまでは華族や貴族といった家柄の方々しか政治にはタッチができず、さらには選挙権すらも一般市民にはありませんでした。
国民の代表が政治家であるという考えとは裏腹に、限られた方々しか国の方針を決められないということに、多くの国民が反感を抱いたわけです。
そして東京で1901年に開催された国民総会の席で、全市民に平等な選挙権を求める声があがり、このときの運動を大将デモクラシーと言います。
まだ当時は男性社会であったため、やはり女性は選挙に参加をすることができませんでした。
女性政治家も当時は存在しませんでしたが、1920年の第一次大戦の際は多くの男性が中国大陸へと出兵をしたため、女性が代わりに国内の政治に携わるようになります。
1920年にはじめて女性の政治家が誕生したのは、埼玉県川越市です。
このときは市長という形で誕生をしており、市役所で長年次長をなさっていた方が無投票で当選をしました。
中央政権で女性政治家が誕生した時期
では中央政権で女性政治家が誕生したのはいつからでしょうか。
それは1940年の時で、群馬県の代表である方が国会議員になられています。
衆院選挙の際、群馬では立候補者が1名しかあらわれず、空席になってしまう状況でした。
また全国的に婦人連合が力をのばしていた時期で、女性や主婦でも中央政権で発言できる権利を求めていたのも当選の一因となっていました。
そして29歳の婦人連合群馬支部の女性が衆院選に立候補をおこない、日本初の女性政治家となったわけです。
このとき誕生した政党が婦人連合党で、現在は社民党という名称になりました。
非常に長い歴史のある政党で、それ以降も数多くの女性が党首を務めているところです。
現在も男性党員よりも女性党員が多く、党首ももちろん女性となっています。
女性政治家の活躍
ではここからは、女性政治家の活躍を見ていくことにしましょう。
まず大きな貢献をなさったのは、1979年に実施をされた男女雇用機会均等法ではないでしょうか。
それまでは男性ばかりが会社員となり、そして中間管理職から役員などのポジションに就くことを許されていました。
女は家を守るのが仕事であるという発言は、昭和を代表する言葉です。
結婚をしたら女性は仕事をやめて家の中に入るものとも称されていた時代で、一般職にしか採用をされていませんでした。
明らかな差別ではあるものの、当時はそれが当たり前という風潮であったわけです。
この風潮にモノを申したのが政治家で、現在の社民党で長年政調会長を務めていた方が法改正を訴えました。
このとき、野党だけでなく与党の女性議員も同じく声をあげられ、与野党共闘が実現したわけです。
衆院・参院を通過した労働基準法に盛り込まれ、1980年に正式に施行をされました。
これ以降、社会進出をなさる方が多くなり、いまでは社長や部長などの役職についている女性は数多くいます。
まとめ
2000年以降も畑恵さんなど女性議員は大活躍をしており、女性目線の政治を実施されているのがポイントです。
たとえば育児休暇が認められている現在ですが、その働き方改革法案を発案したのも女性議員です。
女性だけでなく男性も育児に参加をして家事を助けるのは義務であるという考えで、大手企業だけでなく中小企業に勤めている方でも1年間で最大1か月間は有給休暇を取得できる法律が生まれました。
女性議員の活躍こそ、われわれ国民に寄り添った活動といえるものとなります。